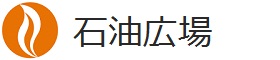全石連 森洋会長 2025年 年頭所感

森洋全石連会長
謹んで新春のお慶びを申し上げます。
組合員の皆様におかれましては、従業員の方々とともに、国民生活や経済活動に欠かせない石油製品の安定供給確保に、日夜、ご尽力いただいておりますことに敬意を表します。
2024年の石油業界は、新春の慶びもつかの間、元日に石川県能登半島沖を震源とする最大震度7の激震が能登半島を襲いました。この震災により、地域住民の方々をはじめ、組合員の皆様の平穏な日常が壊され、電気、ガスといったエネルギーインフラや道路・鉄道といった交通インフラ、そして上下水道などの生活インフラに甚大な被害を及ぼしました。
こうした状況の中、組合員に皆様は、住居が全壊・半壊するなど大きな被害を受け、自らが被災者でありながら、避難所からSSに通ったり、SSに寝泊まりしながら燃料供給を続けられるなど、石油販売業者としての使命感だけで被災者をはじめ、避難所・病院等への燃料供給に尽力され、エネルギー供給の“最後の砦”としての使命を果たされました。
7月に島根県東部で発生した大雨災害では、行政と石油組合、組合員の皆様が連携し、手作業でガソリン携行缶を運ぶなど、孤立地域への燃料供給が行われました。8月末には台風による竜巻が宮崎市内を襲い、下水処理場の発電機用燃料が切れ、地元組合員が燃料の緊急配送要請に迅速に対応されました。さらに9月末には、能登地方を記録的豪雨が襲い、SSも浸水被害に見舞われ、震災復旧工事にさらに遅れが生じる中、被災地の復旧・復興に不可欠な石油製品の供給に懸命に取り組んでおられます。
このように、災害時における地元石油販売業者の皆様の燃料供給対応での貢献は、枚挙に暇がありません。
一方、政府は、原油価格の高騰によるコロナ禍からの経済回復の重荷になる事態を防ぐための時限的・緊急避難的な対策として、「燃料油価格激変緩和対策事業」を2022年1月末に始動しました。その後のロシア・ウクライナ紛争の勃発による原油価格の急騰で、補助額が拡充されるなど、国民生活や経済活動に係る燃料コスト負担の軽減に大きく寄与しました。
しかしながら、事業開始からすでに3年が経過し長期化する中、政府は昨年末に立案した総合経済対策で激変緩和対策事業の出口戦略を発表しました。卸価格の段階で、補助額は昨年12月19日から1ヵ月余りで10円程度縮減されることとなっています。
この激変緩和対策事業により、ガソリンをはじめとした石油製品の価格は約3年にわたり価格抑制が行われてきた結果、一部の安値量販店などによるガソリンのシェア争いや、需要拡大を狙った廉売が各地で散見されるなど、販売競争の激化で多くのSSが急速なマージン低下に見舞われ、危機的な経済状況に陥っています。一方で、従業員の流出を防ぎ、新たな人材を確保していくための持続的な賃上げの取り組みも喫緊の課題となっています。いまこそ、小売業の原点に立ち返り、再投資可能な適正利潤の確保による採算経営の構築が急務です。
他方、最近の政治情勢は、「年収103万円の壁」の引き上げに加え、ガソリン減税が議論の俎上の載せられることとなりました。政府与党の方針では、ガソリン税の旧暫定税率の廃止を含むガソリン減税については、今後、車体課税・燃料課税を含む総合的な観点から検討していくこととされました。いずれに致しましても、石油諸税の問題は多方面に大きな影響を及ぼしますので、引き続き、今後の検討の行方を注視していきます。
世界的に気候変動対策が進展する中、政府は2050年カーボンニュートラルを標榜し、2035年電動車100%方針、あるいはカーボンプライシングなどの施策を進めております。こうした気候変動対策は、我々石油販売業者の主力商品であるガソリンなどの石油製品の需要減をさらに加速させる要因ともなってきます。一方で、エネルギー基本計画等の政府のエネルギー政策においては、地政学リスクの高まりや頻発化・激甚化する自然災害を見据え、エネルギー安全保障の観点から、石油製品の安定供給確保の重要性も盛り込むなど、SSの存続に向け、我々石油販売業界は激しい対応を迫られています。
石油製品の安定供給を維持していくためには、石油販売業界の7割を占める小規模事業者をこれ以上減らしてはならないのです。
各企業の生き残りは自助努力が当然のことですが、国民の暮らしや経済を支え、災害時にはエネルギー供給の“最後の砦”として、SSがその安定供給機能を発揮していくためのビジョンの策定や、SSの次世代化に向けた取り組みを後押していくための支援の継続・拡充につきましても、政府に対し、引き続き、訴えていきます。
2025年 元旦
全国石油商業組合連合会 全国石油業共済協同組合連合会
会 長 森 洋